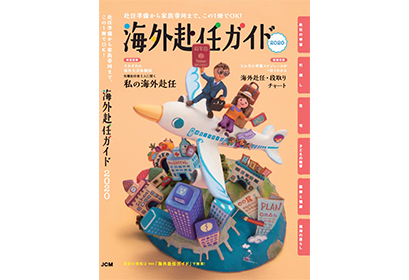2日(月)晴れ。先日、地元紙のコラムに尊敬する市民科学者故・高木仁三郎氏が取り上げられていた。氏は東大で原子力を専攻し、卒業後原発開発のための原子力事業所に勤務。当時の職場の雰囲気が「市民科学者として生きる」(岩波新書)に紹介されている。
2日(月)晴れ。先日、地元紙のコラムに尊敬する市民科学者故・高木仁三郎氏が取り上げられていた。氏は東大で原子力を専攻し、卒業後原発開発のための原子力事業所に勤務。当時の職場の雰囲気が「市民科学者として生きる」(岩波新書)に紹介されている。
なぜか中曽根康弘氏が日本への原発導入に熱心だったこと。原発の効率や推進に関わる部署ばかりが重んじられ、原発の危険性に目を向ける職員は疎んじられた。氏は知れば知るほど疑問が強まり、退社。脱原発の草分けとなる「原子力資料情報室」を設立。
コラムは高木氏の市民科学者としての原点は宮沢賢治の「雨ニモマケズ」の中の「涙」と「オロオロ」にあったと。災難では泣いてオロオロする「人間の顔をした科学」とは人の弱さを受け入れ、学問の思い上がりを絶つことから始まったと訴えたのだと。
 賢治の「われわれはどんな方法で我々に必要な科学をわれわれのものにできるか」という言葉を高木氏は問い続けたのだという。知らなかった。コラム氏は「福島原発の現場では、多くの技術者が汗と涙を流し、オロオロし、懸命に対処している。原子力は「我々に必要な科学か?」と問いかけ、議論を促している。私はこの呼びかけに応じたい。
賢治の「われわれはどんな方法で我々に必要な科学をわれわれのものにできるか」という言葉を高木氏は問い続けたのだという。知らなかった。コラム氏は「福島原発の現場では、多くの技術者が汗と涙を流し、オロオロし、懸命に対処している。原子力は「我々に必要な科学か?」と問いかけ、議論を促している。私はこの呼びかけに応じたい。
生活の見直しは日本人の働き方も検討課題に入れたい。例えば学校、教師の8~9時までの居残り、時には深夜まで残業で残っている学校がある。確かに学校が荒れ、生徒指導で深夜まで対策会議や親との話し合いがしばしばあることは認める。私も経験者だから。
しかし、そうした緊急事態ではなく、上からの管理強化のための雑務、自己評価や生徒の生活点検など、他国では全くやられていない余計な仕事のための残業なのだ。教師の本来の任務は教材研究・授業の準備のはずだ。そんなものは学校でなくても家でもできる。
 現にタイやニュージーランド(NZ)の教師は4時半から5時には帰宅し、教材研究は家でやっていた。日本のおかしさは、校長がそれを許していることだ。NZやドイツでは遅くまでの居残りや休日出勤は校長にとがめられる。エネルギーの無駄遣いではないかと。
現にタイやニュージーランド(NZ)の教師は4時半から5時には帰宅し、教材研究は家でやっていた。日本のおかしさは、校長がそれを許していることだ。NZやドイツでは遅くまでの居残りや休日出勤は校長にとがめられる。エネルギーの無駄遣いではないかと。
日本の場合、さらにおかしいのは、本当に仕事があるのではなく、親の目を気にしての残業や休日出勤があることだ。教委や管理職がそれを「教育熱心」と評価する土壌があるということである。専門家による社会体育への移行も一向に実現せず、教師のボランテイアによる部活動も本務が勤務時間内に終わらない要因となっている。民間企業にしても、一流自動車メーカでさえ、2時間まではサービス残業とするなど、法律違反を堂々とやってのける体質がある。滅私奉公の思想が依然として風土としてある。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。