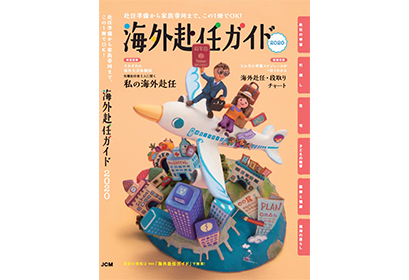7日(火)久しぶりの雨で30度を切りそう。フィンランドの教授、学生、校長の発言を読んでいると、各自が教育哲学を持って完全に自立していることがよくわかる。教授「教師とは目の前の生徒に対して、自分こそが彼らを知っていて、彼らを教えることができると自分を信じることだ。一番の目的は教師としてのアイデンテイテイを持たせること」
7日(火)久しぶりの雨で30度を切りそう。フィンランドの教授、学生、校長の発言を読んでいると、各自が教育哲学を持って完全に自立していることがよくわかる。教授「教師とは目の前の生徒に対して、自分こそが彼らを知っていて、彼らを教えることができると自分を信じることだ。一番の目的は教師としてのアイデンテイテイを持たせること」
次は26歳で教員を志した2児の父親学生。大学で何を学ぶのかという質問に「大学では教科書の使い方を学ぶのではない。わからなかったら赤本があるから、使いたければ使えばいい。けど大学で授業の進め方を教えてくれるわけではない。自分でやってみたい授業の進め方を各自が考えて、大学の授業で発表し、先生と一緒に考えるのだ」
次は教育実習を受け入れる某校の校長「教師になるには学生のプラス面を早く発見して伸ばしてやるのが一番だ。自分の力に自信を持たせ、やる気を起こさせるのだ。これが教師になるためのアイデインテイテイの中核を形成していく。不足のフォローは次の段階だ」
 「実習は学生の希望を尊重する。前回失敗したからもう一度3年生を担当したいとか、歴史を多く教えたいとか。特別支援を必要とする子どもがいるクラスに入りたいとか、目的意識をもって学生が取り組んでいる」これほどの見識のある校長は日本にいるかな?
「実習は学生の希望を尊重する。前回失敗したからもう一度3年生を担当したいとか、歴史を多く教えたいとか。特別支援を必要とする子どもがいるクラスに入りたいとか、目的意識をもって学生が取り組んでいる」これほどの見識のある校長は日本にいるかな?
福田氏は後半で欧州と日本の学力観の違いを比較。「日本人の解釈では正しい答えに合わせるように教え込むことが教育である。その結果、みんな行動は一致する。答えは一つ、知識も一種類しかない。学力向上とは、単一の物差しの序列を上げることにほかならない」
 「西欧の場合、人間は一人ひとり違う。つまり異質のものなので、多様な人間の一致点を少しずつ増やしていき、又それぞれの良いところを組み合わせてもっと大きな力がでるようにコミニュケーション能力を育てようとする。答えは一つではない」
「西欧の場合、人間は一人ひとり違う。つまり異質のものなので、多様な人間の一致点を少しずつ増やしていき、又それぞれの良いところを組み合わせてもっと大きな力がでるようにコミニュケーション能力を育てようとする。答えは一つではない」
このいわば正反対とも見える学力観だからPISA型学力テストは元々西欧型学力を測るように作られており、日本の子どもが読解力が低いと出るのは当然と言えば言える。しかし、はっきりと言えるのは、日本式教育では読解力も判断力もつかないということだ。
私がわずか半年間ではあるが、ニュージーランド語学学校で出会った欧州諸国の若者に比べ日本の若者が(私自身も含めてだが)あらゆる社会的な問題について、或いは人生観について自分の意見を持たないか、持っていても、表現力に欠けることは明白だった。それが日本の教育の仕組みに由来することも又明らかであった。文科省はやれ考える力だ、生きる力だ、自ら判断する力だと言ってきたが、本当にそれを望んだか怪しいものだ。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。