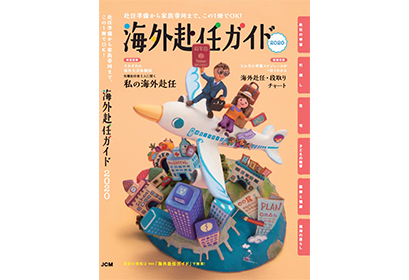7日(水)曇り時々雨。気温1時半で26度。今朝の日報にOECD(経済協力開発機構)が発表した加盟各国の国内総生産(GDP)に占める公的な教育支出の割合について07年(自民党政権下)の調査結果が載っている。今更驚くこともないが28カ国中最下位だった。
7日(水)曇り時々雨。気温1時半で26度。今朝の日報にOECD(経済協力開発機構)が発表した加盟各国の国内総生産(GDP)に占める公的な教育支出の割合について07年(自民党政権下)の調査結果が載っている。今更驚くこともないが28カ国中最下位だった。
日本は03,05年も最下位、04,06年はワースト2位。GDPに占める割合は3.3%で各国平均が4.8%トップはアイスランドの7.0、デンマークの6.6、スエーデンの6.1と続く。下位はスロバキア、チリ。段階別では初中教育と大学など高等教育ではワースト2位。
逆に全教育支出に占める私費負担の割合では33.3%で韓国、チリ、米国に続き4番目に高い。特に大学は67.5%(各国平均30.9%)、幼稚園では56.2%(同20.3%)と高い。又公立中の学級生徒数は33.0人で2番目に多く、小学校28人で3番目に多い。
 これらの結果について日本の文科省は「少人数学級にすれば必ず学力が向上するとは言えない。質の高い教員を確保することも大事だ」などと、恥ずかしいコメントをしている。
これらの結果について日本の文科省は「少人数学級にすれば必ず学力が向上するとは言えない。質の高い教員を確保することも大事だ」などと、恥ずかしいコメントをしている。
世界に例のない管理一辺倒の文教政策で質の高い教員の育成などできるはずもない。
今回でフィンランドの教育に関するレポートを終わりにしたいが、福田氏は結論として「テストのための教育は時代遅れで非効率」と言う項目を掲げ、次のようにいう。テストのための勉強では本当の実力は付かず、子どもたちの能力は開発されない。
米英同様、日本でもこの点をきわめて多くの大人たちが理解していない。ここが一番の問題だとして、元フィンランドの教育省に勤務し、現在米国で銀行マンであるサハルバーグ氏の言葉としてグローバリズムの流れに乗っている米英日の教育を批判。
 「基準化と競争に基く教育の最近の展開は、意味ある人生のために、また知識経済の先に生徒を準備するためには、だんだんと逆効果を及ぼし始めた」生徒たちを学校に閉じ込めて、政府の決めた固定的な知識を注入するような教育は時代に合わないということだ。
「基準化と競争に基く教育の最近の展開は、意味ある人生のために、また知識経済の先に生徒を準備するためには、だんだんと逆効果を及ぼし始めた」生徒たちを学校に閉じ込めて、政府の決めた固定的な知識を注入するような教育は時代に合わないということだ。
日本でも教育改革が叫ばれて久しいが、最近の方向はまるでフィンランドの方向と逆走しているように見える。人事考課制度による教師の管理強化、授業時数増加や学力テスト競争による成果主義の強調。学校5日制さえも崩されそうな情勢である。このままでは日本の教育に未来はない。
私はフィンランドに学べと言いたいけれど、それが面白くないというなら、もう一度江戸時代の教育を見直そうと提案したい。今「教育から見る日本の社会と歴史」という本を読み始めた。これも読み終えたら、是非紹介してみたい。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。