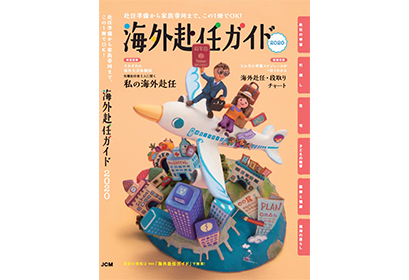14日(火)曇り後晴れ。ようやく猛暑から解放された。3日間の雨の後でテニスができてよかった。民主党代表選で騒々しい毎日だったが、ようやく終わり、菅内閣の続投が決まった。コロコロ変わる内閣総理大臣が再び交替という恥だけは避けられた。
14日(火)曇り後晴れ。ようやく猛暑から解放された。3日間の雨の後でテニスができてよかった。民主党代表選で騒々しい毎日だったが、ようやく終わり、菅内閣の続投が決まった。コロコロ変わる内閣総理大臣が再び交替という恥だけは避けられた。
農業に関わるデータをもう少し見てみる。日本の農業就業人口は毎年十数万人ずつ減り続け、08年で298万人。このうち約半数の140万人を70歳以上の高齢者が占め、20年後を担う39歳以下は35万人にとどまる。同様に漁業人口も60歳以上が5割を占める。
若者が農業に興味関心がないとは思わない。今までの農業が汚い、きつい、のイメージの上に、生活が成り立たないということから農業離れが進んだだけではないか。魅力ある農業政策が示されれば、農業をやりたい人は必ずいるはずである。
 民主党のマニフェストにある「米国との間で自由貿易協定(FTA)を締結し、貿易・投資の自由化を進める」としているのは、農産物の価格保障制度と矛盾するように思われる。今回の代表選で小澤氏は改めて自由化を進める代償としての保障制度課のような発言。
民主党のマニフェストにある「米国との間で自由貿易協定(FTA)を締結し、貿易・投資の自由化を進める」としているのは、農産物の価格保障制度と矛盾するように思われる。今回の代表選で小澤氏は改めて自由化を進める代償としての保障制度課のような発言。
それなら反対だ。欧州での自給率向上の取り組みに学べば、EU域外に対する関税政策、域内への保護政策があって成し遂げたことだ。耕地面積にしても仏を除けばイギリスをはじめ、ほとんど日本より狭い。確固とした食糧安全保障の視点が必要だ。
ただEUの価格保障も過保護といわれるほどになり、農民の意欲や過剰生産が問題になっている。FTAには反対でもJAや自民党の言う言い分には乗らない。彼らは農林省と結託して日本の農業を破壊した元凶だから。若者の意欲を導く価格保障制度が必要だ。
 先日、輸入米に触れたが、日本でも95年に米の輸入が解禁された。WTO(世界貿易機関)により一定量の輸入米購入が義務づけられたのだ。現在77万トンが輸入されている。これは日本一の年間生産量を誇る北海道の生産量63万トン(04)を見ればわかろう。
先日、輸入米に触れたが、日本でも95年に米の輸入が解禁された。WTO(世界貿易機関)により一定量の輸入米購入が義務づけられたのだ。現在77万トンが輸入されている。これは日本一の年間生産量を誇る北海道の生産量63万トン(04)を見ればわかろう。
輸入米の多くは、加工食品や海外援助米として使用されている。だが、処分しきれず、年間10万トンが余る状態にある。輸入米の存在を世間に知らしめしたのは三笠フーズが横流しした事故米問題だった。輸入米をスーパーで目にすることがないからわからないのだ。
農業は食糧問題にとどまらない。農業工学研究所は04年、農林業の多面的機能に関し、洪水防止の経済効果を37兆円、窒素浄化機能が700億円という試算を発表。生態系水質の保全、景観形成といった環境との調和の問題もある。社会共通資本との位置づけもある。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。