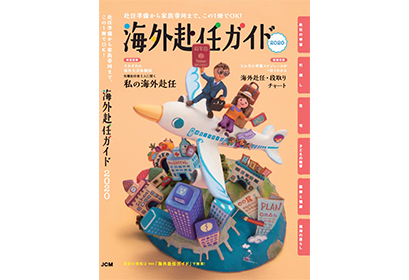17日(金)午前中は雨、午後晴れる。おかげで秋空の下でテニスができた。管改造内閣の顔ぶれが出そろった。肝心の管直人の表情に生気が感じられないのが気になる。マスコミは相変わらず、やれ脱小澤だ、論功行賞だと面白おかしく騒ぎ立てている。
17日(金)午前中は雨、午後晴れる。おかげで秋空の下でテニスができた。管改造内閣の顔ぶれが出そろった。肝心の管直人の表情に生気が感じられないのが気になる。マスコミは相変わらず、やれ脱小澤だ、論功行賞だと面白おかしく騒ぎ立てている。
管直人が強力なリーダーシップを発揮する以外に打開の道はなさそうだが期待薄だな。新文科相に就任する高木義明なる人物を調べてみても、特別教育に関心をもって取り組んできた経歴はない。首相自身の教育への関心度が透けて見えてがっかりである。
日本の教育が昔から儒教の影響を受けてきたと思いがちだが、中世までは圧倒的に仏教の影響下にあった。金沢文庫や足利学校が寺院と深い関係があったことでもわかる。儒教とりわけ朱子学の影響が強くなるのは江戸時代以降である。寛政異学の禁で官学となる。
 江戸幕府が朱子学を重んじたのは、道徳の重視、将軍と旗本・御家人、藩主と家臣、親方と弟子、本家や分家、親子や夫婦関係などあらゆる社会の上下関係の秩序を重んじる秩序観の他に現実社会における有用性について仏教より優れていると考えられた。
江戸幕府が朱子学を重んじたのは、道徳の重視、将軍と旗本・御家人、藩主と家臣、親方と弟子、本家や分家、親子や夫婦関係などあらゆる社会の上下関係の秩序を重んじる秩序観の他に現実社会における有用性について仏教より優れていると考えられた。
近世における教育は先ずは私塾を通して普及した。読み書き、計算を中心とする寺子屋とは違い、塾主の個性がそのまま塾の教育に反映するために、儒学、国学、洋学、武芸など多様な教育内容があり、教育方法でも厳格な注入主義あり、個性重視の塾も多かった。
幕府や藩の規制もほとんどなかったから、入門の規制も一般的になく、著名な塾には全国から入門者が集まった。武士の学校となった藩校は18世紀末(寛政年間)に開設ラッシュとなった。藩校が幕府からも独立し、藩が私塾に干渉することもなかった。
 先日見学した山形庄内藩の致道館の説明にも「致道館教育が生徒の天性に応じて長所の伸長に努め、知識の詰め込みを排して自学自習を重視したのは、すべてこの徂徠学の考えに基づくものです」とある、この徂徠学とは幕府の朱子学ではなく荻生徂徠の教えである。
先日見学した山形庄内藩の致道館の説明にも「致道館教育が生徒の天性に応じて長所の伸長に努め、知識の詰め込みを排して自学自習を重視したのは、すべてこの徂徠学の考えに基づくものです」とある、この徂徠学とは幕府の朱子学ではなく荻生徂徠の教えである。
藩校は儒学を中心にした教養学問を学ぶものと、医学校、洋学校、郷学なども藩校に入るという。幕末時点で255校を数える。新潟にも東京学館高校があるが、全国にある「館」の字のつく学校は、この藩校の影響によるらしい。
藩校は私塾に比べて時代を担うような人材を輩出してこなかったといわれる。確かに緒方洪庵の適塾、吉田松陰の松下村塾、シーボルトの鳴滝塾、本居宣長の鈴の屋などを思い起こせば、その差は何だろう。個性を発揮できる教育の環境とは何かを考えさせる。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。