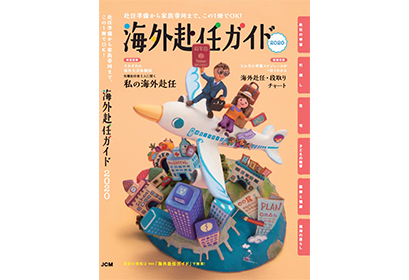21日(火)曇り。尖閣諸島問題で両国が対立を恐れてきちんと交渉のテーブルに着かなかった一例を一つ。1978年の日中平和友好条約の際、訒小平は記者会見で「国交正常化の際、両国はこれに触れないと約束した。一棚上げしても構わない」と述べた。
21日(火)曇り。尖閣諸島問題で両国が対立を恐れてきちんと交渉のテーブルに着かなかった一例を一つ。1978年の日中平和友好条約の際、訒小平は記者会見で「国交正常化の際、両国はこれに触れないと約束した。一棚上げしても構わない」と述べた。
その間、台湾も中国も実効支配を目指して島に上陸した。日本も右翼団体が上陸して日の丸を建てたりしてその都度騒ぎになった。問題は海底資源と漁業資源の問題なのだから、3国共同で開発なり、漁獲をするような話し合いができないものかと思う。
「日本農業はドイツのそれに比べ、気候、土壌に恵まれ、面積当たりの生産効率性は世界一といわれるのにも関わらず、穀物自給率が年々衰退を続け20台に落ち込んだのはなぜ?」と問題提起しているのは新潟県妙高市在住で自然農法を追求している関口博之氏。
 1961年の農業基本法の成立によって、農業の一層の省力化を図るために機械化と化学肥料化が進んだ。この時点では日本の穀物自給率は80%を維持していた。一方で食糧管理法による米だけを偏重する高米価政策により生産過剰となり70年に減反政策が始まる。
1961年の農業基本法の成立によって、農業の一層の省力化を図るために機械化と化学肥料化が進んだ。この時点では日本の穀物自給率は80%を維持していた。一方で食糧管理法による米だけを偏重する高米価政策により生産過剰となり70年に減反政策が始まる。
関口氏はこの時、ドイツのように化学肥料と農薬を少なくする環境保全型農業を選択し、減収分に価格保障をすべきだったと。実際は目先の利益を求める農民や農協、票欲しさに米価を上げ続けることに圧力をかけ続けた自民党農林族が日本農業を衰退させた。
中国からの汚染された農産物の輸入が問題になっているが、実は単位面積当たりの農薬使用量は世界一だとか。少しデータが古いが、96年度の日米比較でも米国の3.4倍、化学肥料でも4倍を超えている。化学肥料による地下水汚染は全国に広がっているという。
 子どもの頃の水田からイナゴやバッタが消え、川で釣れたフナ、ナマズ、ドジョウが消え、田せりも見なくなり、ホタルが見られなくなったのもすべてそのせいだったと気付く。ドイツでも70年代の終わり頃の状況は日本と同じで過剰生産と環境汚染で悩んでいた。
子どもの頃の水田からイナゴやバッタが消え、川で釣れたフナ、ナマズ、ドジョウが消え、田せりも見なくなり、ホタルが見られなくなったのもすべてそのせいだったと気付く。ドイツでも70年代の終わり頃の状況は日本と同じで過剰生産と環境汚染で悩んでいた。
危機感を感じた政府及び各州は80年代の初めに、現在のEUの農業政策に先駆けて、環境保全型の農業経営に補償金を支払う制度に踏み切った。「田園景観維持計画(化学肥料や農薬を禁止する有機農業)」をたて、この計画に寄与する農家に補助金を出す内容。
同じ悩みを抱えていたスイスでもドイツに倣った環境保全型農業への転換をなんと76年に国民投票で77.6%の賛成を得て推進し、自給率を40%から50%に増加させている。政策転換一つでも民主主義の成熟度が左右するのだということを教えてくれる。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。