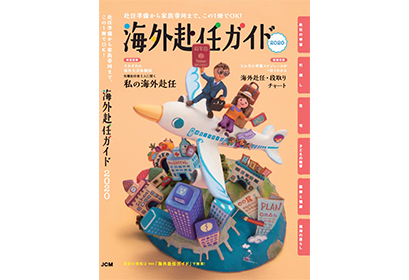28日(火)雨。先日の山歩きでも考えたが、昔は山に入ると、枝おろしをしたり、炭焼きをしている姿をよく見かけたものだが、今はほとんど見かけることはない。日本の山林は今どんな状況にあるのだろう。世界的な山国であるはずだが、木材の自給率も気になる。
28日(火)雨。先日の山歩きでも考えたが、昔は山に入ると、枝おろしをしたり、炭焼きをしている姿をよく見かけたものだが、今はほとんど見かけることはない。日本の山林は今どんな状況にあるのだろう。世界的な山国であるはずだが、木材の自給率も気になる。
海外から帰国すると、日本の森林の豊かさを実感する。日本の国土面積は約3780万ha、そのうち2500万ha(70%)が森林である。森林率でいえば先進国中フィンランドに次いで2位。しかもそのうち1300万ha(50%)が天然林、40%が人工林である。
にもかかわらず、木材の自給率は2000年には20.5%まで落ち込んだ。その後、09年に27.8%まで回復したとはいえ、森林大国としては情けない状況である。1960年の木材の自由化が引き金になり、86.7%あった自給率が農業同様輸出産業の犠牲にされてきた。
 森林にはたくさんの機能がある。評価額順にあげてみると、表面浸食防止、水質浄化、水資源貯留、表層崩壊防止、洪水緩和、保健レクリエーション、二酸化炭素吸収、化石燃料代替。60年代の燃料革命により国産材の需要が減ったことが自給率低下の理由ではない。
森林にはたくさんの機能がある。評価額順にあげてみると、表面浸食防止、水質浄化、水資源貯留、表層崩壊防止、洪水緩和、保健レクリエーション、二酸化炭素吸収、化石燃料代替。60年代の燃料革命により国産材の需要が減ったことが自給率低下の理由ではない。
森林の所有者は林野庁など国有林が30%、都道府県や市町村など公有林が11%、私有林が58%である。戦後の農地改革の対象から森林がはずされたことも影響している。ドイツとの違いを追求している福田誠治氏は「日本は国土の68%という広大な森林面積を持ちながら森を荒廃させ、林業を衰退させ続け、世界最大の木材輸入国へ転落したのは何故?」
ドイツも中世にはブナなどの乱伐によって洪水の被害が頻繁に起こったらしい。現在のドイツでは年間成長量の7割近くの需要を満たすまでに回復している。それを可能にしたのは連邦から6割、州から4割支払われる森林管理農家への手厚い直接保障金だという。
 この保障は下草刈りや間伐など環境保全への貢献に対する正当な報酬であると考えられ、農地から植林による森林への転換が行われる場合にも補助金がでる。市民が税金によって農業を支えることは当然と考えられている。日本のようにすぐばら撒きなどとは言わない。
この保障は下草刈りや間伐など環境保全への貢献に対する正当な報酬であると考えられ、農地から植林による森林への転換が行われる場合にも補助金がでる。市民が税金によって農業を支えることは当然と考えられている。日本のようにすぐばら撒きなどとは言わない。
福田氏は日本の森林再生のため、いくつかの提言をしている。「国内の木材自給は可能であり責務である。森林が環境保全や水資源涵養などへの果たす役割に見合う補助金の支給。個人意欲を削ぐ画一的で統制的な森林政策から、ドイツのように個人意欲を喚起するような政策に転換することだ。植林も画一的な針葉樹ではなく、ドイツのように多種類の樹木育成に対して多くの補償金を払う制度とすれば、保水力の増大だけではなく、病虫害の被害を少なくすることも可能である」と。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。