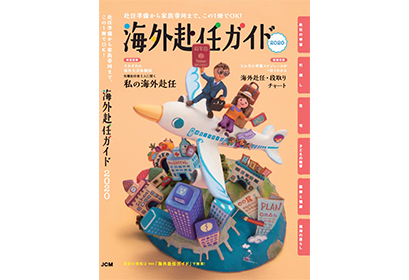19日(火)晴れ。テニス日和。紙新潟日報の社説はなかなか視点が確かで評価しているのだが、今朝の「人勧超え削減どうした」には仰天。しかし、読んでみれば、菅首相が「人勧超え削減」を主張したこと、「民主党の人件費2割削減」の不履行を非難する内容だった。
19日(火)晴れ。テニス日和。紙新潟日報の社説はなかなか視点が確かで評価しているのだが、今朝の「人勧超え削減どうした」には仰天。しかし、読んでみれば、菅首相が「人勧超え削減」を主張したこと、「民主党の人件費2割削減」の不履行を非難する内容だった。
「言行一致は政治家が基本にすべき態度だ」にはまったく同感だ。社説は又「人事院勧告制度は公務員の労働基本権を制約する代償として存在する。勧告を超える引き下げには基本権の在り方の検討が欠かせないし、場合によっては訴訟となる可能性がある」と。
大学で法律を専攻した私にとっては常識に属する事なのだが、世間では案外そうではないなと実感することが労働問題である。労働法の特徴は最低基準を定めたもので、労使交渉によって、労働者に有利になる条件は勿論法律違反にはならないということである。
 先日紹介した有給休暇がその良い例で、日本では最低10日だが、会社が25日を与えても何ら問題ない。ドイツでは最低24日で平均すれば30日だというのは、そのことの証明である。公務員は法の最低基準を守ることが求められる。それを恵まれ過ぎとは言えまい。
先日紹介した有給休暇がその良い例で、日本では最低10日だが、会社が25日を与えても何ら問題ない。ドイツでは最低24日で平均すれば30日だというのは、そのことの証明である。公務員は法の最低基準を守ることが求められる。それを恵まれ過ぎとは言えまい。
公務員が恵まれ過ぎという議論の中で例えば退職金がある。世間には我々が丸々税金をいただいているかのような誤解がある。ほとんどは我々の積立金であり、全国数百万人の積立金の運用益で賄われている。非難さるべきは天下り官僚の退職金である。
もっとおかしいのは、国、地方、行政委員会等特別公務員の給与や手当なのだ。私自身も気づかないできたことを恥ずかしく思うが、国会議員や地方議員の歳費の高さ、行政委員(人事委員、選挙管理員、教育委員、農業委員等々)の報酬の高さ、不合理さである。
 例えば新潟市教育委員会(6名)は定例会は月一回なのに定額の報酬が支払われる。私が昔委嘱された教科書採択委員会は会議の当日の旅費と日当が支払われた。家での作業時間が何倍もかかったことで不満はあったが、これが本来の実費弁済で正しい。
例えば新潟市教育委員会(6名)は定例会は月一回なのに定額の報酬が支払われる。私が昔委嘱された教科書採択委員会は会議の当日の旅費と日当が支払われた。家での作業時間が何倍もかかったことで不満はあったが、これが本来の実費弁済で正しい。
それもこれも諸外国の制度や実態を調べてわかったことで、私を含め、日本人は現状が当たり前だと思わされてきた。そして、官から民へとか、民間並みにとかと言えば、それがいかにも合理的であるかのような雰囲気を作り出している。その結果はどうか。
慢性的な医師不足、看護婦と医師との関係の格差、教員の無免許運転や夜遅くまで学校に居残っている異常さ、保育所の不足、年休さえ自由にとれない雰囲気、育児休暇を男性がとることの困難さ、上げきれないほどの公共のサービスの低下を招いている。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。