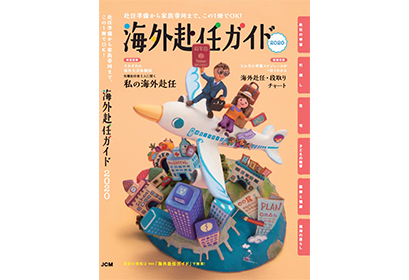6日(土)晴れ。久しぶりに青空が広がった。尖閣ビデオ流出事件はいよいよ内部告発の線が強くなってきた。そもそも事件が起きた直後に公開しておけばよかったものを下手に隠そうとするからこうなる。今のネット社会で素人でもいずれ出ることはわかっていた。
6日(土)晴れ。久しぶりに青空が広がった。尖閣ビデオ流出事件はいよいよ内部告発の線が強くなってきた。そもそも事件が起きた直後に公開しておけばよかったものを下手に隠そうとするからこうなる。今のネット社会で素人でもいずれ出ることはわかっていた。
さて、議会の無駄遣いの話だが、ドイツの地方議会を見てみよう。ドイツの議会も休日や夜間に開催されるため、市民の誰もが立候補を可能としている。議員は名誉職で報酬はなく、実費弁済である。職業は教師や公務員が多く、店員、専業主婦もいる。
木佐茂男氏の「豊かさを生む地方自治」(日本評論社)によれば、議会の開催日数は年間30日ぐらい。属する政党が明白であり、日本のような政党隠しの無所属議員が8割も占めることはあり得ない。国会にあたる連邦議員も同様で専門職で報酬も出るが、2期8年で現場に復帰するのが一般的だという。日本の国会議員のような特権は持たない。
 二世三世などの世襲議員はほとんどいない。教師を含め約4割が公務員(休職)出身。日本と同じ小選挙区比例代表制だが、選挙区の数と同数くらいの比例代表数で後者に重点がある。日本の場合、議会が平日に開かれるから、一般住民の立候補は難しく、地域のボスや建設不動産を含めた中小企業経営者や自営業者が圧倒的で、しばしば利権が露骨に求められることになる。
二世三世などの世襲議員はほとんどいない。教師を含め約4割が公務員(休職)出身。日本と同じ小選挙区比例代表制だが、選挙区の数と同数くらいの比例代表数で後者に重点がある。日本の場合、議会が平日に開かれるから、一般住民の立候補は難しく、地域のボスや建設不動産を含めた中小企業経営者や自営業者が圧倒的で、しばしば利権が露骨に求められることになる。
地方議員を専門職にしているのは欧米ではあり得ず、公務員の立候補を制限しているのも異常である。なぜそうなったのか、戦後の政府官僚が中央集権体制を維持するために機関委任事務や補助金制度などを考えた。議会もいわばその一環としてとらえられたということである。
今になって地方分権だの権限移譲・財源移譲などと騒いでいるが、先ずは議会のあり方を見直すことが必要ではないか。一時期(95年)地方分権委員会が発足し、例えば教育委員会の公選制の復活や教科書検定の廃止、採択の自由化も議論されたが、結局何も変わらなかった。
 日本の官僚制度は元々明治の改革の際ドイツに倣ったものだが、今では似ても似つかないものになっている。ドイツの公務員は日本とは逆に政治に積極的に関わることが求められ、大部分の職員は政党会派に属し、幹部職員は政党の得票率に比例して割り当てられることになっている。
日本の官僚制度は元々明治の改革の際ドイツに倣ったものだが、今では似ても似つかないものになっている。ドイツの公務員は日本とは逆に政治に積極的に関わることが求められ、大部分の職員は政党会派に属し、幹部職員は政党の得票率に比例して割り当てられることになっている。
ドイツの行政が情報公開法を必要としないほど開かれており、公務員は競って市民に情報を公開しようと努めるのだという。官僚に大幅な裁量権を与え、そのかわり責任も厳しく問われる。官僚ポストの課長及び部長以上では全国公募され、それ以下は庁内公募のシステムもある。天下りもなく、汚職には厳しい罰則がある。食事接待を受けて起訴された例もあるという。ドイツの勤務評価は上司が行うが、本人開示が不可欠だから、真剣に向き合うことが求められるという。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。