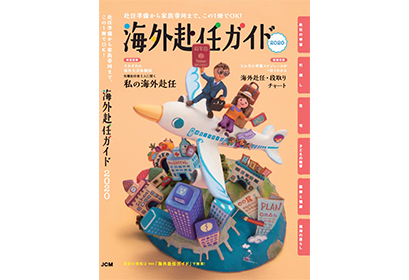22日(月)雨。柳田法相が辞任した。改めて日本の政治家の資質に疑問を感じる。それ以上に腹が立つのは、マスコミのコメンテーターたちの言動だ。みんな、したり顔でこきおろして済ませている。そんなに能力がないことを知っていたなら就任時に言え!
22日(月)雨。柳田法相が辞任した。改めて日本の政治家の資質に疑問を感じる。それ以上に腹が立つのは、マスコミのコメンテーターたちの言動だ。みんな、したり顔でこきおろして済ませている。そんなに能力がないことを知っていたなら就任時に言え!
今回の政権交代だって、当初はあれほど持ち上げていたではないか。今度は自民党と一緒になって政権批判一辺倒だ。問題の本質を分析して提言するとか、反省の言葉がない。このまま管政権が野垂れ死にして、自民党が復活するようなら絶望的だ。
11月21日版のしんぶん赤旗日曜版に企業の内部留保の記事が載っている。原発問題を一時お休みして、企業の社会的責任について考えてみたい。この問題でも欧米、特に欧州の企業に比べ、日本の企業は利益優先が余りに露骨で横暴だと思うことが多々あった。
 私の教え子の母親はドイツマルチン・ルター大学日本語学科の教授で、数年前、「日独青少年非行の比較研究」プロジェクトを立ち上げ、何度も来日し、生徒、教師、親にインタビューを繰り返し、研究成果をまとめたが、研究を支えたのは何とベンツ社だった。
私の教え子の母親はドイツマルチン・ルター大学日本語学科の教授で、数年前、「日独青少年非行の比較研究」プロジェクトを立ち上げ、何度も来日し、生徒、教師、親にインタビューを繰り返し、研究成果をまとめたが、研究を支えたのは何とベンツ社だった。
一見、企業活動と非行は何のかかわりもないように見える。でもドイツでは当たり前のことだという話だった。企業のイメージアップだけではなく、企業の存続に不可欠な社会の持続的発展に対して必要なコストを払い、未来に対しての投資と考えるのだという。
当初はアメリカ型の市場中心主義へのアンチテーゼとして語られたというが、今ではむしろ企業活動の根幹として根付いている。アメリカでも90年代後半から、企業責任が強く主張されるようになった。東南アジア地域での米企業による強制労働、低賃金労働、児童労働、セクシャルハラスメントなどの事件が続発し、不買運動が背景にあるという。
 日本はと言えば「企業の社会的責任」はアメリカより昔からあると言う。各企業の家訓、例え三井家家訓に「多くをむさぼると紛糾のもととなる」住友家には「廉恥を重んじ、貧汚の所為あるべからず」などとあるとの解説もあるが、守られているかどうか怪しい。
日本はと言えば「企業の社会的責任」はアメリカより昔からあると言う。各企業の家訓、例え三井家家訓に「多くをむさぼると紛糾のもととなる」住友家には「廉恥を重んじ、貧汚の所為あるべからず」などとあるとの解説もあるが、守られているかどうか怪しい。
日本の企業はまだまだ寄付や慈善事業への協力程度にとどまっている程度ではないか。例えばパラリンピックの支援や障害者施設への支援、NGOやNPOへの支援も欧米企業に比べると、その規模や支援額などで到底及ばないのが実態のようである。これは政治の問題とも深くかかわるが、政府が企業に社会的負担を求める姿勢が極めて弱いことも特徴になっている。次に取り上げる社会保険料の企業負担の少なさや、莫大な内部留保を許すのも日本特有のありようと言っていい。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。