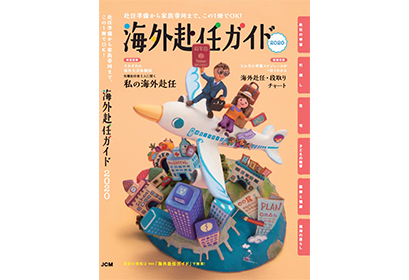5日(水)曇り。1924年というのは、孫文死去1年前のことである。私は孫文が大好きで、中国、台湾、シンガポールの記念館又は居所先を訪ね歩いた。孫文が好きなのは、その思想の奥行きの深さ、包容力の大きさである。それはベトナムのホーチミンに匹敵する。
5日(水)曇り。1924年というのは、孫文死去1年前のことである。私は孫文が大好きで、中国、台湾、シンガポールの記念館又は居所先を訪ね歩いた。孫文が好きなのは、その思想の奥行きの深さ、包容力の大きさである。それはベトナムのホーチミンに匹敵する。
人生60年中、半生が亡命生活だった。そのうち一番多く訪れたのはシンガポールと日本の8回だった。シンガポール滞在中の孫文を調べたことがあるが、隠れ家での滞在中は箸や中国語の使用等中国人であることにこだわり、祖国への思いは誰よりも強かった。
日本への憧れは強く、それだけに日本が王道を投げ捨て、西洋に取り入る道を選んだことへの失望は大きかった。1914年に日本の犬養毅(後首相)に当てた色紙「民意に依る国は栄え、民意に逆らう国は亡ぶ」は精いっぱいの皮肉だったのではと私には思える。
 孫文は「華橋は革命の母である」とも言っているが、その華橋に対し常々説いていたのは、礼儀正しくあれと言うことだった。立ち小便、道路での痰や唾を吐くこと、大声で喚くこと等を強く戒めた。今の中国人をみたら、彼は大きく顔をしかめるに違いない。
孫文は「華橋は革命の母である」とも言っているが、その華橋に対し常々説いていたのは、礼儀正しくあれと言うことだった。立ち小便、道路での痰や唾を吐くこと、大声で喚くこと等を強く戒めた。今の中国人をみたら、彼は大きく顔をしかめるに違いない。
私が10年ほど前スイスのホテルのレストラン会場で目撃した光景はまさにそのままだった。私たち夫婦をはじめ白人などの先客がいるところへ、中国人の団体客が大声で入って来る気配。スイス人スタッフは一斉にビュッフェスタイルの果物類を片づけ始めた。
おそらく、2泊目だったのだろう。聞いてみたら、バナナやリンゴをあるだけ全部持ち去るのだと顔をしかめて言うのだった。他の客の存在などまるで眼中にないかの如き振舞いなのである。その他、バスや列車の列に並ばないなどその傍若無人さは目に余る。
 かく言う日本人はどうなのか。幕末から明治にかけて日本(新潟)を訪れた西洋人(イサベラバード)は日本人の礼儀正したと町の綺麗さ(ゴミがない)に驚嘆しているが、立ち小便、痰や唾を吐く悪習は私が子どもの頃まで田舎には残っていた。
かく言う日本人はどうなのか。幕末から明治にかけて日本(新潟)を訪れた西洋人(イサベラバード)は日本人の礼儀正したと町の綺麗さ(ゴミがない)に驚嘆しているが、立ち小便、痰や唾を吐く悪習は私が子どもの頃まで田舎には残っていた。
新潟市内でも外国人に礼儀正しく見えた裏には近代化に見識のあった幕末の新潟奉行川村修就や明治の開化県令とうたわれた楠本正隆によるさまざまな改革令に負うところが大きい。つまり、衣食足りて礼節を知るの例えの如しである。ベトナム、タイも同様だろう。
中国が先進国の仲間入りをするためには、日本がそうしてきたように、海外に出て洗練された文化や人々に学ぶ過程が必要なのである。現に多くの中国人が海外に出かけているし、その経験が国内に生かされる日が必ず来る。日本が30年前に経験したことに過ぎない。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。