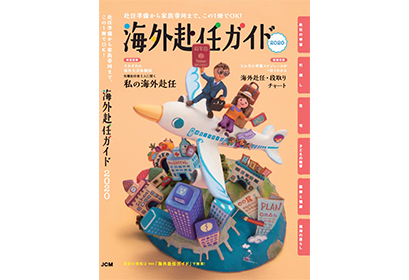13日(木)晴れ。ネットのニュースを見ていたら、面白い記事に出くわした。台湾で歴史上の偉大な中国人人気ランキングである。1位は断トツで孫文なのは納得できるが、2位に毛沢東が登場し、蒋介石は3位続いて息子の蔣経国が上がったというのだ。
13日(木)晴れ。ネットのニュースを見ていたら、面白い記事に出くわした。台湾で歴史上の偉大な中国人人気ランキングである。1位は断トツで孫文なのは納得できるが、2位に毛沢東が登場し、蒋介石は3位続いて息子の蔣経国が上がったというのだ。
もっともその後、選択肢の中になぜ共産主義者をという抗議があり、やり直したらしい。今年は辛亥革命から100年目にあたる。清朝時代の諸外国による反植民地状態を脱し、民族、民主、民権の3民主義を掲げて近代国家への道を歩めたことへの評価が孫文であろう。
それにしても、革命当初の毛沢東の業績は理解できるとしても、大躍進政策はおろか、文化大革命のような馬鹿げた政策を掲げ、鄧小平をはじめその後継者たちも毛沢東の亡霊から脱しきれずに天安門事件を引き起こすような人物をなぜ評価できるのだろう。
 前号の続きになる。AMF(アジア通貨基金)構想が浮上したのは97年のタイ通貨危機の際だと言う。当時も円は80円を割り、日本は通貨介入をやって乗りきった。大蔵省(当時)内で、このままドルに翻弄される状況を放置するのかという声が高まったという。
前号の続きになる。AMF(アジア通貨基金)構想が浮上したのは97年のタイ通貨危機の際だと言う。当時も円は80円を割り、日本は通貨介入をやって乗りきった。大蔵省(当時)内で、このままドルに翻弄される状況を放置するのかという声が高まったという。
ニュース番組の時々コメンテーターでミスター円と異名をとる榊原英資(国際金融局長)がその構想の中心にいたらしい。榊原は資金集めに奔走し、タイ支援の枠組みをアジア全域に広げ、円を中心としたアジア共通通貨への道を切り開こうと言う壮大な構想だった。
当時中国の立場は弱く、アメリカは中国に反対するよう圧力をかけ、中国は賛成も反対もしない形で受け入れた。こうしてAMF構想は潰された。昨年11月のASEANにおける中国の動きはこの時の学習に基いてのものだという。中国外交は憎らしいほどしたたかだ。
 中国の共産政権が続く限り、こうした政治的構想で同盟することはないであろうが、経済は生き物で、円建て、人民元だての貿易は確実にその額を増やしているようだ。例えば00年下期に36%だった輸出決済の円建て比率は昨年上期には41%まで上昇したという。
中国の共産政権が続く限り、こうした政治的構想で同盟することはないであろうが、経済は生き物で、円建て、人民元だての貿易は確実にその額を増やしているようだ。例えば00年下期に36%だった輸出決済の円建て比率は昨年上期には41%まで上昇したという。
中国の海外企業買収ばかりが非難されているが、日本企業が10年に手がけた海外企業買収は479件と過去最高。投資額も約3兆3200億円と前年比1.8倍に膨らんだ。ステラス製薬、NTTが米国と南アフリカで大型買収に踏み切り、「強い円」を武器にしたのだ。
来月2月パリで開催予定のG20 財務省・中央銀行総裁会議で再びIMF体制の見直しが話し合われると言う。フランスのサルコジはドル支配体制からの脱却を公言し、中国も同じ方向である。日本はどういう態度をとるのか、とれるのかアメリカからの自立にかかる。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。