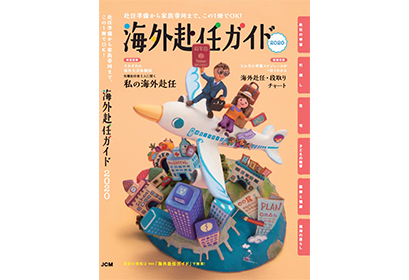20日(木)曇り。夫婦別姓反対論者たちが必ず持ち出すのは、別姓によって家族の絆や一体感が失われるとか夫婦喧嘩が増えるなどと言う人さえいる。私はドイツ、NZ、ベトナム、中国の家庭を最低1か月以上体験しているが、家族の絆の強さは日本以上と感じた。
20日(木)曇り。夫婦別姓反対論者たちが必ず持ち出すのは、別姓によって家族の絆や一体感が失われるとか夫婦喧嘩が増えるなどと言う人さえいる。私はドイツ、NZ、ベトナム、中国の家庭を最低1か月以上体験しているが、家族の絆の強さは日本以上と感じた。
各国の姓は歴史的に言えば例えば儒教の影響の強いアジアでは夫の姓と言うより父の姓を名乗る場合が多かった。中国が別姓になったのは革命後のことだ。韓国や台湾が別姓なのは父親の姓を名乗るからだ。欧米はどうか、古くは夫の姓優先だったが今や別姓は権利。
ドイツのように夫婦の姓を並べて名乗る人もいる。それも権利だと言うことである。いずれにせよ、別姓によって家族の絆云々は全く根拠がない。日本人が昨年度の時事通信の世論調査でも別姓反対が55.8%を占めたというのも、情緒に流された意見ではないか。
 そこで思い出したのが学生時代に学んだ「民法典論争」である。明治政府は幕末に諸外国から押し付けられた不平等条約の改定に悩んだ。諸外国が不平等を押し付ける口実に使ったのが「日本には憲法はおろか、刑法も商法も民法もないじゃないか」だった。
そこで思い出したのが学生時代に学んだ「民法典論争」である。明治政府は幕末に諸外国から押し付けられた不平等条約の改定に悩んだ。諸外国が不平等を押し付ける口実に使ったのが「日本には憲法はおろか、刑法も商法も民法もないじゃないか」だった。
そこで当時のお雇い外国人を活用しての法整備だった。民法についてはフランス民法の直輸入だったが、顧問だったボアソナードから日本の実情にあった法整備を勧められる有様だった。その出来上がった案に対して噛みついたのがドイツ帰りの穂積八束だった。
彼が仕掛けた「民法出でて忠孝亡ぶ」だった。当時の法律学校の学者をあげての論争になった。仏派の明治、法政VS独派の中央、早稲田、東大という構図である。勝利したのは穂積の東大派だった。そして成立したのが女性の地位を徹底的に貶めた旧民法だった。
 その当時も穂積らが持ち出したのが「日本の伝統の家長制を否定するもの」と「妻が夫を訴えるなどあってはならない」と主張したのだ。日本の伝統が家長制だと言うのも歴史的事実に反する。例えば平安時代までは女性の嫁入りは一般的ではなく、女性の地位は高かった。鎌倉時代でも女地頭もいたし、財産相続権は女性にもあった。
その当時も穂積らが持ち出したのが「日本の伝統の家長制を否定するもの」と「妻が夫を訴えるなどあってはならない」と主張したのだ。日本の伝統が家長制だと言うのも歴史的事実に反する。例えば平安時代までは女性の嫁入りは一般的ではなく、女性の地位は高かった。鎌倉時代でも女地頭もいたし、財産相続権は女性にもあった。
男尊女卑が徹底するのは江戸時代だったが、それも武家階級を中心とする上流階級での話だ。武士階級でさえ婚姻の際の妻の持参金には強い発言権があった。詳しくは次号に譲るが、旧民法ではその妻の地位を無能力者と規定し、相続権、親権、妻からの離婚請求権も否定し、戸主による一方的な離縁や姦通罪を女性だけに限るなどの規定を盛り込んだのだ。これらは日本の伝統とは無縁で、戸主に強大な権限を持たせ、天皇制国家の末端組織に位置ずけて、支配をスムースに考えた制度にほかならないのである。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。