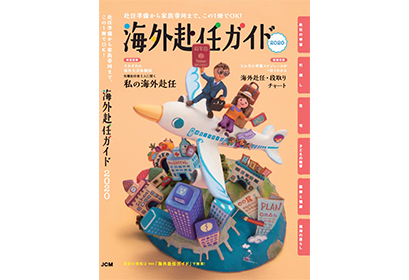21日(金)曇り。私は読んでいないが、ネットで見つけた「三くだり半と縁切り寺」という著書からの引用で興味深かった。江戸時代の結婚についての内容だ。江戸時代の人口は3200万人中、武士6~7%、町人5=6%、神官、僧侶、エタ・非人で3.1%残りが農民。
21日(金)曇り。私は読んでいないが、ネットで見つけた「三くだり半と縁切り寺」という著書からの引用で興味深かった。江戸時代の結婚についての内容だ。江戸時代の人口は3200万人中、武士6~7%、町人5=6%、神官、僧侶、エタ・非人で3.1%残りが農民。
江戸時代は法治国家ではないから、庶民の生活を律する法律はなく、幕府による生活規制(慶安のお触れ書きとか5人組に関する掟など)しかなかったのは当然だ。昔からの慣習によっていただろう。三くだり半と言うのは男性が一方的に離縁するときの書きつけ。
研究によれば、三くだり半が夫から妻に渡されたからといって、妻が泣く泣く実家に帰ったわけではないという。江戸時代、離婚は恥でも何でもなかった。気に入らない男性をさっさと見捨てた女性もいたという。我々が今まで抱いていたイメージとは随分違う。
 日本の離婚率(人口1000人当たりの件数)は統計が始まった1883年(明治16年)が3.38、旧民法(妻の地位の低下)の定着に従って離婚率は下がり、戦前の私が生まれた43年の離婚率は0.68、戦後右翼グループが新民法で離婚率が増えたと宣伝している。
日本の離婚率(人口1000人当たりの件数)は統計が始まった1883年(明治16年)が3.38、旧民法(妻の地位の低下)の定着に従って離婚率は下がり、戦前の私が生まれた43年の離婚率は0.68、戦後右翼グループが新民法で離婚率が増えたと宣伝している。
事実はどうか。敗戦直後の47年が1.02、その後長らく1.0未満に減少。再び1.0を超えたのが72年の1.02、1.5を超えるのがバブル崩壊後の93年の1.52である。そして07年の数値が2.02である。それでも欧米諸国に比べればまだまだ低い優等国である。
明治初年の離婚率の高さから、江戸時代の離婚率は4.0%代だったとの推定が為されている。中でも武士階級の離婚率は10%を超え、再婚率は50%を超えていたという。「貞女二夫にまみえず」といったことは男性の願望に過ぎなかったということである。
 百姓町人はどうか。女性の地位はもっと高かったのは間違いない。女性は武士階級に比べれば貴重な労働力であり、軽い扱いを受けたはずはないのである。江戸時代はむしろ今と同じ協議離婚が主体で、夫からの一方的な追い出し離縁は例外だったらしいのだ。
百姓町人はどうか。女性の地位はもっと高かったのは間違いない。女性は武士階級に比べれば貴重な労働力であり、軽い扱いを受けたはずはないのである。江戸時代はむしろ今と同じ協議離婚が主体で、夫からの一方的な追い出し離縁は例外だったらしいのだ。
離婚条件は今より女性に有利だった。例えば離婚理由に挙げられているのは1.夫が妻の承諾なしに妻の衣装など持参財産を質に入れたとき。2.妻と別居もしくは音信不通つまり事実上の離婚状態が3~4年続いた時。3.髪を切ってでも離婚を願う時。
4.夫が家出して12カ月(古くは10か月)が過ぎたとき。5.比丘尼(縁切り寺)へかけ込んで、3カ年が経過した時。これでわかるように、右翼が主張している日本の家族制度というのは明治以降の話で、決して日本の伝統でも何でもないということである。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。