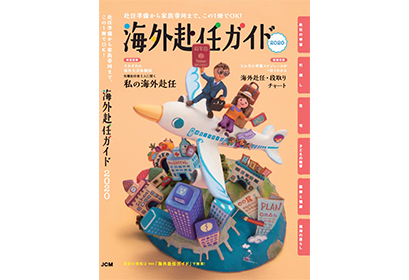31日(月)晴れ。青空が広がった一日だったが、気温が低いから雪が解けない。新潟の雪は全国ニュースになる。私の新任の赴任地津南町は積雪が3mを超えたし、さらに雪深い入広瀬は4mを超えた。新潟市内は散歩道に数センチの雪が残っている程度である。
31日(月)晴れ。青空が広がった一日だったが、気温が低いから雪が解けない。新潟の雪は全国ニュースになる。私の新任の赴任地津南町は積雪が3mを超えたし、さらに雪深い入広瀬は4mを超えた。新潟市内は散歩道に数センチの雪が残っている程度である。
家族問題を締めくくりたい。研究者によれば例えば西欧においては「これこそ西ヨーロッパ家族であるという類型は存在しない」という。私の見聞によっても、個々の自立性の高さはやはり西欧だなあと思っても、家族の有り様は日本と大きくは違わない。
核家族化が進み、地域が崩壊して近所づきあいが少ない点でも共通だったし、都会と田舎の違いも似ていると思わされた。逆にアジア(タイやベトナム)の田舎では50年前の日本を見るようでもあり、地域で助け合って生きる姿に感動したこともあった。
 最近は児童虐待や家族観、夫婦間のDVが問題になり、そのことを保守派等は戦後の民法改正による家族制度の崩壊に求めているが、すでに明らかにしたように、例えば離婚率一つをとっても、旧民法下の明治時代の方が現在の1.5倍にもあり、根拠のない話である。
最近は児童虐待や家族観、夫婦間のDVが問題になり、そのことを保守派等は戦後の民法改正による家族制度の崩壊に求めているが、すでに明らかにしたように、例えば離婚率一つをとっても、旧民法下の明治時代の方が現在の1.5倍にもあり、根拠のない話である。
ドイツの心理学者リヒターの「病める家族」によれば、患者の家族を劇場家族:良い家族をお芝居のように演じている家族、要塞家族:自分たち以外はすべて敵とみなし、対抗することで絆を確認する家族、サナトリウム家族:互いに傷を舐めあうような家族。
確かに毎日のように報道される家族に絡む事件を見ていると、暗澹たる気持ちになるが、これもある研究者によれば、昔からあったことで件数的には減っているのであり、報道が増えたのだと言う方を信じたい。大半の家族は健全な営みや役割を担っていると思いたい。
 確かに「隣の芝生は綺麗に見える」ことはあるが、「渡る世間は鬼ばかり」に描かれる家族内の軋轢やいざこざはどこの家にもあるからこそ、誰にも思い当たることがあって、ホッとできるから長寿番組になっているとも考えられる。サザエさんの番組も同様だ。
確かに「隣の芝生は綺麗に見える」ことはあるが、「渡る世間は鬼ばかり」に描かれる家族内の軋轢やいざこざはどこの家にもあるからこそ、誰にも思い当たることがあって、ホッとできるから長寿番組になっているとも考えられる。サザエさんの番組も同様だ。
私は家族の授業には最低4時間はかけ、新旧民法の比較に2時間、諸外国の例に1時間、最後に討論や作文に1時間を割いた。今大学4年の子たちの作文に「私にとっての家族とは」心の休まる場所、ケンカばっかりだけどなくてはならない場所、とっても大切な存在
誰もが理想的な家族を持ちたいと願っている。家族に国家は立ち入らない原則は世界共通だと思うが、夫婦別姓問題や財産相続、結婚離婚等それを妨げる制度があれば、それは正されなければならない。法の下の平等は人類が獲得した普遍的価値なのだから。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。