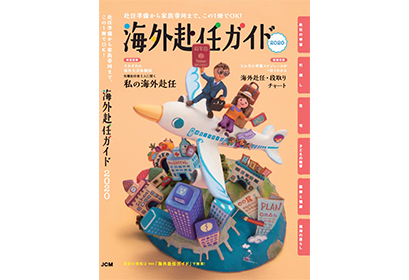9日(水)あられ後晴れ。3権分立はフランス革命に大きな影響を与えたモンテスキューの理論で今や近代民主主義の鉄則ともいえる原則となっている。しかし、その度合いは国によってかなりの差がある。OECD諸国では欧州、アメリカ、日本は最低だろう。
9日(水)あられ後晴れ。3権分立はフランス革命に大きな影響を与えたモンテスキューの理論で今や近代民主主義の鉄則ともいえる原則となっている。しかし、その度合いは国によってかなりの差がある。OECD諸国では欧州、アメリカ、日本は最低だろう。
検察制度の問題を見てきたが、最後に検察と裁判所の関係、特に裁判所が独立していない実態を報告して締めくくりとしたい。日本では旧憲法下でも形の上では3権分立になっていたが、実際は天皇に権力が集中し、裁判も天皇の名において行われた。
戦後の憲法改正によって、建前上、3権分立は実質化されたはずだった。しかし、現実には行政権が徐々に司法権を侵食し、司法権内部でさえ最高裁を頂点とする司法行政が人事や異動権限を握り、裁判官の判決にさえ影響を与えるまでになってしまった。
 憲法では最高裁長官は、内閣が指名し、天皇が任命する。最高裁その他の裁判官は、内閣が任命する。下級裁判所裁判官は最高裁の指名した者の名簿によって内閣が任命する。議会の同意を必要としないこの規定自体も問題だが、それでも戦後は抑制が利いていた。
憲法では最高裁長官は、内閣が指名し、天皇が任命する。最高裁その他の裁判官は、内閣が任命する。下級裁判所裁判官は最高裁の指名した者の名簿によって内閣が任命する。議会の同意を必要としないこの規定自体も問題だが、それでも戦後は抑制が利いていた。
例えば最高裁15人の裁判官は暗黙の了解の下に裁判官、検察官、弁護士出身者からそれぞれ5人ずつ各界からの推薦により選出されていた。それを完全に崩したのは田中角栄内閣である。政府の意に沿わない判決を書く弁護士出身者を避け、元駐米大使を起用した。
さらに行政による司法への人事介入が進んだのは1969年に起きた北海道長沼町に自衛隊のナイキ地対空ミサイル基地建設をめぐる行政訴訟である。自衛隊の要請に応えて農林省が国有保安林の伐採を許可したことに住民が反発自衛隊は憲法違反だと訴えた事件である。
 この裁判で札幌地裁所長平賀健太(人事権を握る)が担当裁判官である福島重雄氏に手紙を送り、住民の訴えを却下するよう「アドバイス」した。福島氏はこれを司法の独立を脅かすものとして手紙を公表した。(平賀書簡問題)福島裁判官はめげず違憲判決を下した。
この裁判で札幌地裁所長平賀健太(人事権を握る)が担当裁判官である福島重雄氏に手紙を送り、住民の訴えを却下するよう「アドバイス」した。福島氏はこれを司法の独立を脅かすものとして手紙を公表した。(平賀書簡問題)福島裁判官はめげず違憲判決を下した。
最高裁はこの問題で平賀健太を注意処分にしながら、東京に栄転させた。一方福島氏は家裁等への左遷を繰り返した。後日抗議声明を発表して辞職、弁護士に転身した。福島氏が当時青年法律家協会という団体に属していたが、71年同団体の宮本判事補を再任拒否。
以後行政及び最高裁事務総局による司法介入は露骨になる一方だった。右翼ジャーナリズムは「青法協は反体制の左傾団体」とのレッテルを貼り、現在、裁判官はこの団体から抜けた。こんな状況下で行政に不利な判決が出るはずもない。恐ろしい国だ。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。