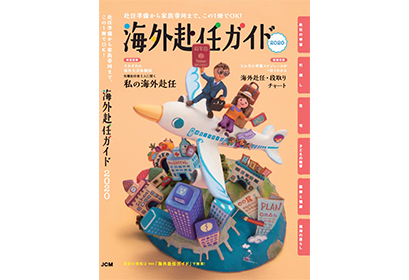24日(木)晴れ。戦後の憲法改正で天皇は主権者から象徴に変わったのだから、天皇及び皇族の有り方を定めた「皇室典範」は新憲法の諸原則に従って全面改正されるべきだった。旧憲法下のそれは憲法の上に位置づけられ、議会の同意すら必要とされなかった。
24日(木)晴れ。戦後の憲法改正で天皇は主権者から象徴に変わったのだから、天皇及び皇族の有り方を定めた「皇室典範」は新憲法の諸原則に従って全面改正されるべきだった。旧憲法下のそれは憲法の上に位置づけられ、議会の同意すら必要とされなかった。
旧皇室典範は12章62条からなり、改正によって現在の5章37条に改正された。ところが、天皇の地位を男系に限るとか、天皇、皇太子、皇太孫の成年は18年とする、天皇及び皇族は養子をすることができない等、明らかに憲法違反にあたる規定を残してしまった。
これは憲法及び皇室典範の改正の指示をしたGHQ内部に日本の皇室典範が天皇の神格性を維持するために考え出した規定であることを深く理解していなかったこと、加えて出来るだけ神格性を残したいと考えた国体護持派の抵抗が功を奏した形になった。
 憲法第3条には「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う」として、象徴である所以を明記したのである。さらに念を押すかのように4条には「国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」とした。
憲法第3条には「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う」として、象徴である所以を明記したのである。さらに念を押すかのように4条には「国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」とした。
戦後アメリカ人のバイニング夫人がGHQの推薦によって、当時の明人皇太子(現天皇)の家庭教師となった。昭和天皇は面白くなかったらしいが、GHQに取り入る気持ちもあって了承した。夫人は弟義宮や姉たちに英語を教え、皇女たちには聖書も教えた。
義宮が聖書に興味を示したことが後日昭和天皇の知るところとなり、叱責したと河原氏の著書で紹介されている。そんなわけで、現天皇は若い頃からリベラルで開明的に育ったと見てよい。記者会見での言葉を拾い集めれば、「象徴」の意味を十分理解されている。
 桜井よしこ氏や石原慎太郎都知事等天皇の元首化を目指している人々にとっては憲法1条~3条は目ざわり極まりないわけである。憲法第6条にある総理大臣や最高裁長官の任命権や7条の国事行為(国会召集や解散)も全く形式的なものであって天皇に拒否権はない。
桜井よしこ氏や石原慎太郎都知事等天皇の元首化を目指している人々にとっては憲法1条~3条は目ざわり極まりないわけである。憲法第6条にある総理大臣や最高裁長官の任命権や7条の国事行為(国会召集や解散)も全く形式的なものであって天皇に拒否権はない。
旧皇室典範のどこがどう変わったのかを見ると。例えば「祖宗の皇統にして男系の男子」を単に「皇統に属する男系の男子」と改めた。それより重大な改正は第4条の「皇子孫の皇位を継承するは嫡出を先にす皇庶子孫の・・」ということは側室が予定されていた。
孝明、明治、大正天皇はそれぞれ側室の子であり、この規定が生きていたということにほかならない。昭和天皇も生まれてくる子が女の子ばかりで、周囲は盛んに側室を勧めたがそれを拒否した経緯がある。そして6人目にようやく現天皇が生まれ、事なきを得た。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。